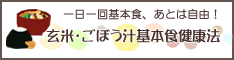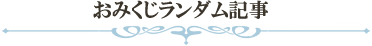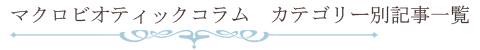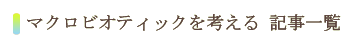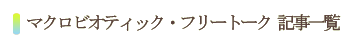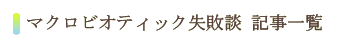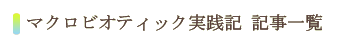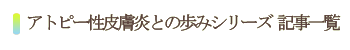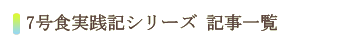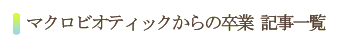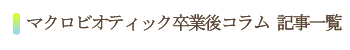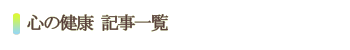今年の夏、にんじんりんごジュースに頼りすぎ、他にまともな食事を取らない生活を送ったために栄養失調でフラフラになって六日間ほど寝込むハメになったわけだが。
(このときの体調不良について詳しくはこちら→「マクロビオティック実践の果てに病に堕ちる」)
そもそも、なぜにんじんりんごジュースというものを食生活に取り入れようと思ったのか。もとをただせば、それは私がマクロビオティックの実践にマンネリ感を覚え始めていたからだった。
マクロビオティックの知識を得れば、これさえ食べていれば間違いないという食材がわかる。
たとえばごぼう、玉ねぎ、にんじん、小松菜、かぼちゃ、大根、きのこ。このへんを冷蔵庫に常備しておいて、あとはそれらを野菜炒めにしたり、海藻を加え全部一緒に煮込んで汁物にしたり……。
玄米ご飯に、常備野菜で作ったおかずを一品。それで健康でいられるのだ。スーパーに行ってもどんな野菜を買おうか悩まないで済むし、献立もワンパターンで良いのだから楽ちん。
マクロビオティックの知恵とは何て合理的なんだろう、料理に手間をかけるのがあまり得意でない私にはぴったりだ! と、ずっと楽しく暮らしていた。
閉塞感を覚える
だが。マクロビオティックの実践も三年目に入り、マクロビオティックが「特別なこと」ではなく「自然な、当たり前のこと」として生活に定着してくるにつれ、私は閉塞感を覚えるようになった。
マクロビオティックが身についたなんて喜ぶべきことのはずで、確かに、何も考えなくてもマクロビオティックが実践できてしまうのは素晴らしいことなのだが、そこには発展がない。
「トマトやナスは陰性だから食べない方がいいよね。果物も控えた方がいいね。私は陰性ぎみだから、陽性のごぼうやかぼちゃを食べたらいいよね。海藻も食べなきゃね。きのこや葉野菜で適度な陰性さも付け加えないとね。」
思考回路がそんな感じで固定されて、食に関しては他のことを考えなくなっていた。停滞していた。
飽きる
極端に言うと、私はマクロビオティックに飽きてきていた。
決められたワクやルールの中で、小さくまとまって生きているような小粒感。マクロビオティックという目に見えないくらいの薄い膜が自分のまわりを覆っているような気がして、その膜を破りたくて躍起になった。
それで、マクロビオティックではない健康法にがむしゃらに飛びついた。にんじんりんごジュースなんて、マクロビオティックでは良しとされなさそうなものに、良しとされなさそうだからこそ手を出した。
結果、痛い目を見たわけだが……。
それでも今回の挑戦と失敗は、マクロビオティック生活に間違いなく彩りを与えてくれた。大コケして、初めて気づき得たことがあったのだ。
たとえば、今までは空腹は無条件で薬と思ってきたけれど、栄養バランスが取れた上での空腹じゃなければ飢餓となり、倒れてしまうのだということ。
定番の常備野菜が優れものであることは間違いないけれど、他にも様々な野菜を食生活に取り入れていくことで、楽しさも出るし、体に活力もみなぎってくるということ。
マクロビオティックをはみ出すことで、マクロビオティックを再発見する。
故きを温ねて新しきを知る、ならぬ、新しきを温ねて故きを知る……といったところか。
マクロビオティックをはみ出すことの大事さ
マクロビオティックというのは、一通り学び終えて、体調も良い感じで落ち着くときが来る。そこで、人によっては、私のように「飽き」が来るかもしれない。
そんなときはマクロビオティックをどんどんはみ出して、「こんなことして大丈夫だろうか?」ということに挑戦してみたら良いと思うのだ。
失敗もあるだろうが、新たな学びも必ずある。
私はこれからも、興味のわいたことは気軽に試してみるという姿勢を大事にしたいと思っている。
マクロビオティックからときに離れ、再び寄り添い。陰と陽の相克で発展! という無双原理を心に、生きていきたい。
【マクロビオティック卒業後の食事法について】
追記:その後、マクロビオティックを卒業し、自分オリジナルの健康道に移行しました。↓
↑「玄米・ごぼう汁基本食」を食べたらあとは何を食べても自由という食事法です。
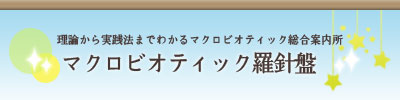
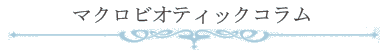
 栄養失調~いわゆる夏バテ:後編-食べ物はバランスよく、たくさんの種類を摂るのが大事
栄養失調~いわゆる夏バテ:後編-食べ物はバランスよく、たくさんの種類を摂るのが大事 生きていれば風邪くらいひくさ~マクロビオティックをやっていても
生きていれば風邪くらいひくさ~マクロビオティックをやっていても